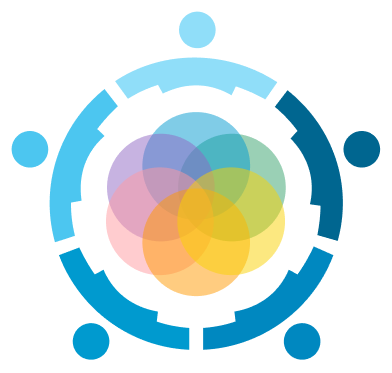職場定着・雇用継続のための支援
医療支援
発達障害のある方は、これまでの学校や職場での失敗経験や周囲に理解してもらえない苦悩、疎外感を重ねていく過程で、自己有用感や自己肯定感を育むことができずに、人を避けて内向的になったり、抑うつやそのほかの精神症状が出たりするケースが少なくありません。
周囲の変化や仕事に対するプレッシャーなどのストレスから、就労にともなう精神症状の悪化について心配される声もよく耳にします。就労が、二次障害である精神疾患に与える影響の把握は非常に難しいところですが、本人の生活歴、教育歴、就業歴の聞き取りや、感覚や物事をとらえる際の特徴など発達障害の特性について、ていねいにアセスメントすることに加えて精神科医などの医療機関と連携することが重要です。
本人や家族においては、発達障害の初期の診断にとどまらず、その後の就労継続のためにも医療機関と上手にかかわりをもっておくことをおすすめします。
関連する資料
医療機関と就労支援機関との連携に関する資料を紹介します。就労支援機関と精神科医療との連携で押さえるべき視点や効果的な情報交換・共有の方法などについて、わかりやすくまとめられたマニュアルです。 本マニュアルは、就労支援機関と医療機関の双方が共通して押さえておきたい視点などをまとめた「共通編」と、就労支援機関が医療機関と関わる際に押さえてほしい視点などをまとめた「就労支援機関編」、医療機関が就労支援機関の役割や障害者雇用施策について理解を深める「医療機関編」に分かれていることが特徴です。 双方の役割や強みを理解することが連携の基本です。医療機関との連携を考える際にはぜひ、ご活用ください。- 就労支援と精神科医療の情報交換マニュアル(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)
参考になった
| 258