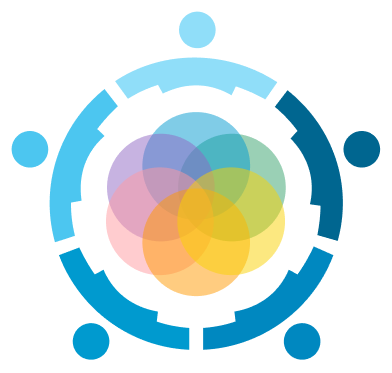就職に向けた準備を始める
就職を考えている方へ
本格的な就職活動に入る前に、押さえてほしい4つのステップがあります。ひとりで抱え込まずに、必要に応じて専門家に相談する、支援機関を活用するなどして無理のないスケジュールを組みましょう。大学や高等学校などに在学中の方は、まずは学生支援室や進路指導の先生に相談することをおすすめします。
〇職業の方向性を決める 自己理解と仕事理解
ステップ1:自分を知る
実際に働き・暮らすのは自分自身です。まずは将来の夢や希望と、今の自分の姿を整理すること、いわゆる自己分析から始めましょう。自己分析では、これまでの生き方やエピソードを振り返り、性格、大切に思うことや価値観、行動傾向などを整理し、自分の強みや配慮、支援が必要なことなどを掘り起こします。発達障害の特性の一つに、想像性・イマジネーションの困難さ(相手の気持ちを想像する、他者から自分がどうみえているかなどの理解の難しさなど)があります。ご家族やご自身をよく知る他者(学校の先生や医療機関、支援機関の方など)から、客観的な意見(強みなどのアピールポイントなど)を教えてもらいましょう。 あまり耳なじみのないことばかと思いますが、就業支援に関する専門用語で”職業準備性(レディネス)”ということばがあります。働く上で必要とされる能力を「疾病や障害を管理する力」、「日常生活を遂行する力」、「職業生活を遂行する力」、「職務を遂行する力」の4つに分け、苦手さや困難さがある場合は、必要に応じて訓練で能力向上をはかったり、支援や周囲からの配慮により補ったりすることで、働くために必要な準備が整うという考え方です。今の自分にどのような能力があるのか、どの部分で周りからの手助けが必要かを考えるヒントにしてみるのもよいかもしれません。詳しくは、関連記事の「職業準備性(レディネス)とは」をご参照ください。 〇雇用市場の調査 適性把握とターゲットの絞り込みステップ2:企業や仕事を知る
「この業界で働きたい」「この企業で働きたい」と目標がはっきりしている方であれば、実際に働いている方の話を聞いたり、職場を見学させてもらうことをおすすめします。また、ほかの業種や企業にも視野を広げてみてください。できれば同じように障害がありながら働いている先輩から、職場や暮らしの中で苦労された話や周りの人から助けてもらった体験談などを聞かせてもらいましょう。身近にそのような方がいない場合は、ウェブ上にある体験談なども参考になりますが、正しい情報かどうかはわかりません。 地域障害者職業センターやハローワークなどでは、障害のある方向けの就職セミナー、企業説明会や職場見学会を随時開催しています。もちろんほかの人の経験ですから、そのすべてがご自身に当てはまるわけではないかもしれませんが、将来の職業生活のイメージづくりの参考になるでしょう。 まだ具体的な目標が固まっていない方も、職場で働く方から講話を聞くことや、障害のある方の働く姿、暮らしぶりを知ることから始めましょう。当事者の経験談を聞くためには、当事者会や就労移行支援など、多くの人が集まる場所を訪ねてみてください。 また、地域障害者職業センターでの職務試行法(職業評価などを目的とした職場実習)や就労移行支援事業所での職場実習、学校でのインターンシップの機会は、自分自身の職業上の可能性や将来の職業生活で押さえるべきポイントなどを明確に知る良い機会です。 〇求職活動ステップ3:職場を知る
業種や企業などの志望先を絞り込めたら、次はターゲットである業種や企業に関する、より具体的な情報取集の段階です。セミナーや会社説明会は、興味のある業界・企業をチェックする、就職活動の実質的な第一歩です。基本的なマナーやルールも確認しておく必要があります。インターンシップの機会などを積極的に活用し、実際の職場でどのように働くのか/働き続けられるのか、職場の雰囲気はどうかなどの生きた情報を得るようにしましょう。 障害特性などで配慮が必要な場合は、企業に個別に相談することもできますが、企業に対する要望や依頼を適切に伝えるためには、学生支援室やハローワーク、就職エージェント、就労支援機関などの支援機関を通じて相談することをおすすめします。ステップ4:採用に向けた対策をする
まず、資格要件や採用試験の内容などを確認します。会社説明会の段階で履歴書・エントリーシート持参という場合もあります。自分の将来を左右するかもしれない1枚と思い、基本を押さえた履歴書を1枚つくっておくとよいでしょう。- 履歴書・職務経歴書の書き方(ハローワーク)
参考になった
| 214